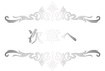あなたを買います。
診断メーカー様(http://shindanmaker.com/563925)より
「グラ青の今日のパラレルは カジノディーラー×美容師 なんてどうでしょうか 」
ディーラーグラウス×美容師青藍パラレル。スペース無視3240文字。
※BLです※
カジノディーラーも美容師も内情は全く知りません。捏造です。
全国のカジノディーラーさんと美容師さん、ごめんなさい。
カジノディーラーと
美容師

チリリン、と軽やかな鈴の音が鳴る。
それに重なるように「いらっしゃい」と言う声が出迎える。
白を基調にしたこの空間は、あなたを引き立たせるだけに存在しているようですね――カジノで働く者が夜の華たちに美辞麗句を並べるための表現は……昼間に言うのは恥ずかしいので口にしたことはない。
これはホストだったらもっとさらっと言えるのだろうか。
しかし、必要以上に客と会話することを禁じられているディーラーは、そういうことには慣れていない。そんな無駄話をしなくて済むからこの仕事を選んだのだが、今となってはその選択が間違っていたのではないかとすら思う。
「今日も揃える程度で?」
「ええ。身だしなみに気を使う仕事なもので」
「大変ですね」
さらり、と彼の手が髪を梳いていく。冷たい手が耳をかすめる。
たったそれだけのことに、心臓が跳ね上がりそうだ。
彼はこの店の美容師。
たまたま通りがかった時に見惚れて、予約もないのに入ってしまって、そこでまたたまたま手が空いていたから、と切ってもらって……それ以来、私はこの店に通っている。
頻繁に通うせいであまり切る必要もない髪に、彼は丁寧に櫛を通していく。
その櫛の感触も、耳元でシャリ、シャリと鳴るハサミの音すら心地いい。
「お疲れですね」
まどろんでいたらしい。
鏡の中であなたが笑っている。
少しマッサージしますね、と耳元で囁かれ、頭頂部から肩にかけてゆっくりと手が滑っていく。
凝っていると言われたのは肩だけだろうか。
この時だけは、いつも緊張でガチガチになっているのだが。
「昼夜逆転しているお仕事は大変でしょう?」
彼は私がカジノのディーラーだということを知っている。
さすがにうちの店に遊びに来ることは無いから想像する程度だろうが、夜の仕事、ということだけはわかっているようだ。
夜の仕事に間違いはないが、ディーラーはホストなどとは少し違う。
客と会話が弾むことなどない。ゲームのホストとしての公平性のためだ。
チップの計算を間違えるわけにはいかないので、アルコールを摂ることなどほとんど無いと言っていい。
長年勤めていれば親しい客も贔屓にしてくれる客もいるが、だからと言ってゲーム中に会話はしない。
客商売のくせに無愛想だと思うのだが、そこが真面目だ、という評価を頂くのだから世の中はわからないものだ。
それでもディーラーとしての仕事を離れれば、客の隣に座って付き合うことはある。
さすがに客と店の外で会ったり、ましてや朝まで共にすることはしないが……そこまでやればもっと儲かるだろう。
また、そうやって媚びていればいい女性客より厄介なのは男性客だ。
高級カジノと銘打っているだけのことはあって、ここに来る男性客は皆それなりの地位に就いている。当然、話の内容も専門的になる。
そういう連中はディーラーもホストも同じだろう、と見下した目で見る。
ホストの中には、わざとお堅い話題を振られて泣かされる者もいる。
自分は客と会話をする機会はほとんどないが、それでも何か振られた時のために、必死で知識を付ける毎日だ。
ウイットに富んだ返事を返すことができれば、奴らの見る目が変わる。
社内に、期待に添える返事を返してくれる部下には恵まれていないのだろうか。
難しい議論に満足すると大目にチップをはずんでくれるから、いないほうが好都合ではある。
こっちはこっちで面倒なことこの上ない。
しかし、女のように性欲に塗れた目で見て来ないだけましかもしれない。
「そうでもありません。昼間に寝ているだけですから」
羽振りのいい女性客に朝まで、とねだられたことは1度や2度ではない。
だが、一線は越えない。
彼に対する操のようなものだと思う。
我ながら純情過ぎて笑うしかない。
夜の仕事、と聞いて、香水と酒の匂いを撒き散らして女に媚を売って稼いでいると……そんな金で自分の時間を買っていると、そう思っているかもしれないのに。
「早く終わらせますね」
「ゆっくりやって下さい」
他愛もない会話。
本当はもっとあなたが知りたい。でも、聞けない。
常連とはいえたかが客の1人にプライベートをペラペラ喋るわけがない。
苦労して聞き出した内容をつなげてみれば、1人暮らしだということ。まだ結婚はしていないということ。特定の恋人はいないこと――。
「平日休みだし、安定しているわけでもないし。将来的に不安なのかもしれませんね」
「でも好きでなった仕事なんでしょう?」
「ええ。ひとの髪を触るの、好きなんです」
照れたようにはにかむ笑みに、心臓を鷲掴みにされた気分だ。
この人が髪を触るのが好きだと言うから、手触りがいいようにシャンプーもノンシリコンの高いものを揃えた。
風呂上がりには馬油の入ったトリートメント。
疲れきって風呂などやめて眠ってしまおうと思う日だって、髪のことを思えばシャワーだけでも浴びる。
ワックスで固めたままでは髪によくない。
ずっと、ずっと、こうして髪に触れていてほしい。
この先も、何年も。
いや、叶うことなら一生。
「でも、もう辞めようかと思うんです」
「……何故!?」
甘い妄想から引きずり出され、私は思わず振り返った。
鏡ではない本物のあなたが目を丸くする。
「実家から、もう帰って来いと言われているので」
聞けば彼の父は名の知れた企業家。
兄もそのグループ会社の数社を任されているのだそうだ。
次男ということで好きなようにさせてもらっていたが、もうそろそろ戻って一翼を担ってくれとの打診があるのだと言う。
高校を出て美容師の専門学校からこの道に進んだけれど、もともと父の会社に入るというレールは敷かれていたそうで、幼少の頃から経済学だのは叩き込まれているのだとか。
どうりでただの美容師にしては奥深い返答が返って来ると思った。
「しがない美容師よりはずっとモテますよねぇ」
それでも数年は勉強漬けの毎日になるんでしょうね、と彼は笑う。
いなくなってしまう。
あなたがいなくなったら、私は誰に髪を切ってもらえばいいんだ。
いや、美容室などいくらでもある。
美容師だって掃いて捨てる程いるし、彼より腕のいい美容師だってそれこそごまんといるだろう。
でも。
でも……。
「なりたかった仕事じゃないんですか!?」
思わず声を荒げる。
椅子に座ったままだから詰め寄ることはできないけれど、それでも圧倒されたのか、彼が数歩後ずさった。
「美容師。なりたかったんでしょう!? そう簡単に辞めてしまっていいんですか!?」
「……そうなんですけど」
彼はいつもの笑みを浮かべた。
「数年だけでも好きなことをさせて貰ったし、……もう、いいかな、って」
嘘だ。
数年で諦められるような仕事であるはずがない。
あんなに楽しそうに髪に触れていたのに。あんなに幸せそうに笑っていたのに。
今、彼が浮かべている笑みは全く違う。
何の感情もない、いや、負の感情を隠そうとする笑みだ。
そんな顔で笑うあなたは見たくない――。
「だ、だったら、私があなたを買います。あなたがその会社に入って一生のうちに生みだす利益、それをお支払いします。だから、」
ああ、何を言っているんだ。
いくら売れっ子のディーラーでも給料なんてたかが知れている。
それに比べて彼は未来の重役だ。
頭の中で計算式を弾く。
ディーラー1カ月の給料+チップとして頂く分×35年+賞与が年2回。
+途中で昇格するだろうから上乗せされる金額。
更に、常連のお客様から貢ぎ物として頂く現物も全て換金。
貯めていた貯金。
……それで、いくらになる?
全財産つぎ込んで足りるかどうか。いや、足らしてみせる。
一生、身を削る思いで働いてでも、必ず。
「だから、」
「あなたの美容師でいろ、と?」
「え、ええ。まぁ」
その人は大きな目を瞬かせて、それから俯いた。
結った髪から覗く耳が赤いのは、決して自分が抱いている感情と同じものではない、と思うけれど。
「兄が……何て言うか」
「一生幸せにしますからっ!」
「それは嫁に下さいとか言う時の台詞ですよ?」
「うっ」
嫁に来てくれても一向に構いません。
さすがに、それは言えない。